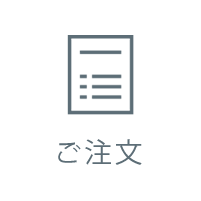クレンゼ キットとは
WHAT'S CLEANSE KIT
効率的・効果的な細菌・ウイルス対策を行うための予防活動キットです。

抗菌・抗ウイルス加工技技術
「クレンゼ スプレー」
”もの”の細菌・ウイルス対策には、
抗菌・抗ウイルス性のある固定化抗菌成分「Etak(イータック)」入りのクレンゼ スプレーが効果的です。
使い方は簡単!皆がよく触れる場所(コンタクトポイント※)に週1回噴霧するだけです。
是非、皆さんの学校、企業内でも実施いただき効果をお試しください。
※コンタクトポイント:たくさんの人の手が触れる環境表面のことです。

週1回の噴霧でOK
クレンゼ スプレー噴霧後約1週間、抗菌・抗ウイルス効果が持続します。
※使用状況によっては持続力が異なります。
※効果はクレンゼ スプレーを噴霧した表面部分のみに限られます。
詳しくみる元に戻す


高い安全性
口腔衛生用抗菌剤(口の中の消毒薬)をベースにした成分を使用しており、
各種試験にて高い安全性を確認しています。
詳しくみる元に戻す
「クレンゼ成分(Etak)は口腔内の治療や洗浄に使用されている成分から生まれた、化粧品成分として国際的表示名称(INCI)に登録されている化合物ですので、どんな場所にも安心してお使いいただけます。
| 試験項目 | 試験結果 |
|---|---|
| 皮膚一次刺激性 試験 |
無刺激性 |
| 皮膚感作性 試験 |
陰性 |
| 変異原性 試験 |
陰性 |
| 急性経口毒性 試験 |
2,000mg/kg以上 |
| 眼刺激性 試験 |
無刺激性 |
| 皮膚連続刺激性 試験 |
無視出来る程度 |
各種試験において、極めて高い安全性が確認されました。

多様な細菌・ウイルスに対する効果
クレンゼ スプレーを噴霧した表面部分に付いた特定のウイルスの数を減らし、特定の細菌の増殖を抑えます。約30種類の微生物(細菌・真菌)やウイルスに対しての効果を確認しています。
クレンゼ スプレー 抗微生物スペクトル
クレンゼ スプレー成分は、以下の細菌、ウイルス、真菌への効果を確認しています。

※注意:上記は「クレンゼ スプレー液」での効果を検証した結果です。